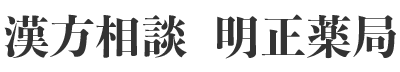むくみ(浮腫)の漢方治療
- 足のむくみが気になる方
- 手足や顔などがむくむ
- むくみと冷えが気になる方
- むくみの漢方薬を知りたい方
目次
むくみ(浮腫)と漢方薬
漢方医学では、人体には気(き)・血(けつ)・水(すい)があり、これらが順調に体内を巡ることで正常な生体環境が保たれると考えられています。
「気」とは内蔵機能の働きや生命エネルギーの事を指し、「血」は血液とその栄養を指し、「水」は血液以外の水分・栄養分・潤いを指します。
このうちの「水」の巡りが悪くなって異常を起こした状態を水毒(すいどく)や水滞(すいたい)と呼びます。
むくみも水毒・水滞の一種なのです。
ただし、むくみが起きるのに「水」だけが原因となるのではなく、「気」「血」も関係することが多いのです。
気は体を動かすためのエネルギーでもあり、気の力が足りないと水がうまく流れてくれなくなります。(腎臓の力が弱いと不要になった水分を体外に出せなくなり、水毒・水滞を起こします。発汗する力が足りない場合も同様です。)
血の流れが悪くなると、血液中の水分が血管外へ漏れ出してむくみになることがあります。夕方足がむくむ場合などがそれに当てはまります。
したがいまして、漢方でむくみを改善させる場合、「水」が滞り重視しながら、「気」「血」の状況も判断することが重要です。
むくみの治療で用いる漢方薬のタイプ
水を巡らせてむくみを改善する漢方薬
主な症状-むくみ、小水の量が少ない、口が渇くなど。
代表処方-五苓散(ごれいさん)、猪苓湯(ちょれいとう)、防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)
腎経(泌尿器・ホルモン系)を良くしながら、利水によりむくみを改善する漢方薬
主な症状-むくみ、足腰がだるい、疲れやすい、夜間尿、下痢または便秘傾向など
代表処方-八味地黄丸(はちみじおうがん)、真武湯(しんぶとう)、牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)
婦人科系を整え、血行改善をしながらむくみを改善する漢方薬
主な症状-むくみやすい、月経不順、月経痛、冷え症など
代表処方-当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)、桃核承気(とうかくじょうきとう)、桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)など。
その他-腹水や胸水、心臓ぜんそくなどの水の停滞
九檳呉茯(きゅうびんごぶく)、柴苓湯(さいれいとう)、木防已湯(もくぼういとう)などを状態に合わせて使用します。
まとめ
食事-塩分や油物の取り過ぎに気をつけ、緑黄色野菜をしっかり食べるように心がけましょう。
運動-適度な運動は血行改善とともにリンパ流れを良くして、むくみを改善していきます。
保温-体を冷やさない、とくに下半身の保温を心がけましょう。
睡眠-なるべく11時頃までにふとんに入りましょう。
リラックス-ストレスが強いと交感神経が高まり、末梢血流が悪くなります。ストレスをため込まずにリラックスできる環境を作りましょう。